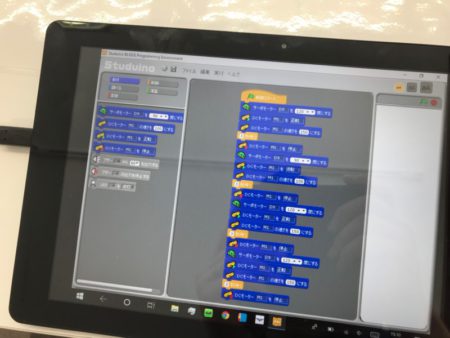探究学習講座vol.2「投資家・ギャンブラー編」開講!
こんにちは!スタッフの熊谷です。
今日は夏の探究学習講座第2弾
「投資家・ギャンブラー編」を開催しました![]()
投資家は、あらゆる事象の起こりうる可能性を考え、お金を賭ける仕事です。
そこには『確率』が深く関係しており、今日の探究学習でも子どもたちは『投資家』として様々な確率に触れました。

サイコロやトランプを使ったカジノゲームで、
「アタリ」「ハズレ」を体験しながら『確率』についての実体験をしました。

教科学習の中で行われる『確率』はとても難しく、苦手を感じる子も多いです。
しかし、ゲームなどを通して楽しく経験した『確率』は、子どもたちにポジティブな記憶とともに残り、教科学習をする際にもスムーズに取り組んでくれるようになります。
また、今回『確率』を刺激されたことによって、普段の生活の中でも『確率』を意識し、考えてくれるようになるでしょう。
探究学習によって良質な刺激をされるとにより、お子様たちは様々なことに興味をもち、自ら調べ、学び出すようになってくれます。
ぜひこの素晴らしい学びを多くのお子様に体感してもらいたいと思います。
ご興味ありましたら教室までお問い合わせください!